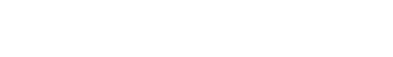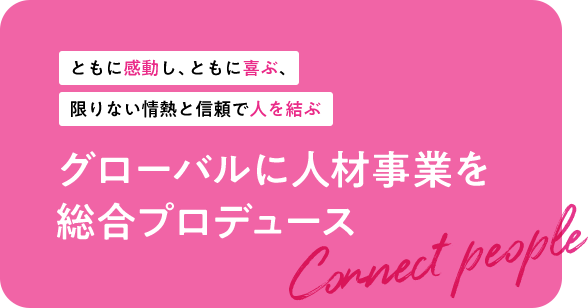



人材紹介・人材派遣事業
人材派遣・人材紹介・紹介予定派遣・業務委託と人材に
関わるあらゆるサービスを提供。オフィスワークから専門的業務、福祉・介護、ITと幅広い業種・職種に対応します。
お仕事をお探しの方

居宅・訪問介護看護事業
「ケアプランセンター」「訪問介護ステーション」「障がい福祉相談支援事業」を行っています。経験豊富なマネージャーが、現象にとらわれず原因を見据えアセスメントを組み各ケースに合ったサービスを熟練ヘルパーが実行します。地域密着、ご利用者様と豊かな心を育む「はぐみ」です。
介護・看護・福祉サービスをご希望の方


留学生支援事業
外国人の若い世代の安定的な雇用創出に向けて外国人介護福祉士を育成、日本で介護職に従事する人材を輩出しています。
外国人介護留学生の受入れをお考えの企業の方